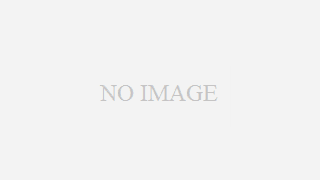 腸をきれいにする食品
腸をきれいにする食品 腸内環境を整え免疫力向上、便秘、ガン、糖尿病、アトピーを防ぐリンゴは万能薬
中性脂肪や有害重金属に吸着し体外に排出する以前から、果物の栄養や機能性を研究し、その優れた健康効果に魅了されてきました。私自身、朝はリンゴやバナナなどをよく食べますし、体調を崩してしまった方々にもお勧めしています。今の季節、旬でおいしいリン...
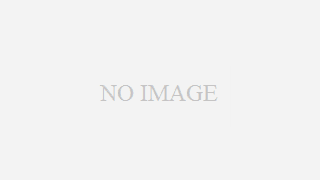 腸をきれいにする食品
腸をきれいにする食品 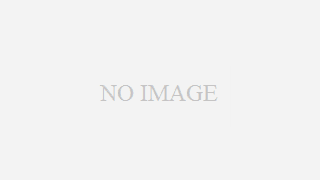 腸をきれいにする食品
腸をきれいにする食品 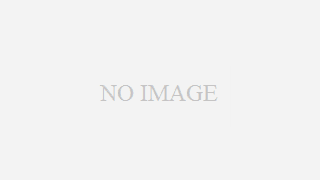 腸をきれいにする食品
腸をきれいにする食品