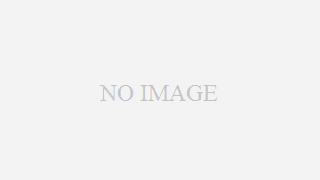 腸の自己診断
腸の自己診断 腹式呼吸 リラックス による 効果
腹式呼吸 リラックス による 効果 について紹介します。おなかの筋肉を使って深く息を吸ったり吐いたりする腹式呼吸。自律神経をリラックス・モードにする効果があります。おなかの筋肉を使って深く息を吸ったり吐いたりする腹式呼吸。自律神経をリラック...
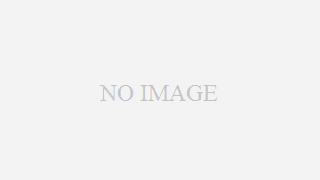 腸の自己診断
腸の自己診断 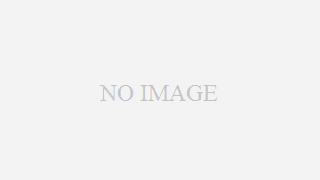 腸の自己診断
腸の自己診断 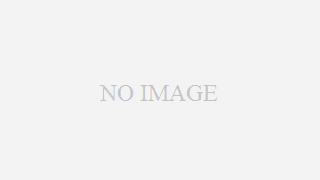 腸の自己診断
腸の自己診断